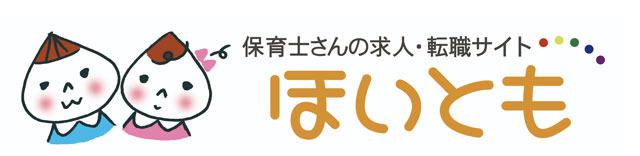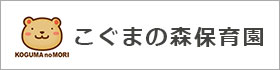2025.02.12
お役立ち情報
手間をかけずに子どもの創造性を引き出す保育園の作品展示会

2月に作品展や絵画展を行う保育園・幼稚園が多いようです。できれば子どもたちの創造性を存分に引き出して、一人ひとりの成長を感じられる行事にしたいものです。でも実際は日々の業務をこなしながら準備や指導をするのはたいへん。今回は最小限の準備で、子どもたちが自主的に楽しく作品づくりに取り組める工夫、手間をかけない展示のコツなどを紹介します。
最小限の材料でできるテーマ選び
作品づくりには材料が必要ですが、まず準備が大変なものは避けましょう。折り紙、画用紙、シール、園庭で集められる自然素材など、身近にあるものがベストです。新聞紙、お菓子の空き箱、トイレットペーパーの芯などは、事前に保護者に協力をお願いするのもアリですね。作品づくりも制作の工程や負担が少ないテーマを選ぶことがポイントです。子どもたちが無理なく、自然に夢中になれる題材を選べば、指導の時間も減らすことができます。例えば…
【色と形の世界】
材料は画用紙とシールだけでOK。子どもたちが好きな色の画用紙に、好きな色のシールを貼って、好きな形を描いていきます。2〜3歳でも簡単にできますし、色選びなどで個性も出しやすいテーマです。
【おててでアート】
ブルーシートなどを用意する必要はありますが、材料は画用紙と絵の具だけです。自分の手で直に絵の具にふれ、体を大きく動かして描くフィンガーペイント。最初は恐る恐る絵の具をさわっていた子どもたちも、次第に手の汚れなどを気にせず、夢中になって取り組みます。
【みんなでつくる森】
園庭で集めた葉っぱや枝が材料です。子どもたちはいろんな形の葉っぱがあることを学び、みんなで作ることで協力することも覚えます。大きな作品になるので、見栄えも抜群です。
展示は「手間をかけずに映える」工夫を
◆1週目/テーマ決め・材料準備
◆2週目/個人作品づくり(1日15〜20分)
◆3週目/共同製作(子どもたち同士で進めやすい方法で)
◆4週目/仕上げ、展示の準備 …という具合です。
展示にもできるだけ手間をかけたくないですね。例えば作品の説明書きはフォーマットを作っておくと便利です。項目は「テーマ」「使った材料」「工夫したポイント」くらいで十分。そしてテーマごとにコーナー展示をすると、保護者も見やすくなります。
画用紙の作品はマスキングテープで貼るだけにすれば、壁を汚さず片付けも簡単です。紙皿アートやモビールは天井から吊るすだけで立体感が出て、写真映えすること間違いなし。手をかけなくても、ちょっとした工夫で素敵な展示になるはずです。
子どもたちの自主性を引き出す作品展アイデア
自主性や創造性を引き出すためには「作成途中」を大事にするのがポイントです。作品展というと「きれいに完成させなきゃ」と思いがちです。でも子どもたちにとって、作品づくりのプロセスも大切な成長の証。まずは作成途中に「ここ、すごいね!」「がんばって考えたね!」と褒めてあげましょう。子どもたちも「これでいいんだ」と安心して進められるはずです。
また、完成品だけを展示するのではなく、「作っている途中のがんばり」「試行錯誤のあしあと」などを見せるのもひとつのアイデアです。例えば制作プロセスを写真に収め、「ここを工夫中!」「いまいっしょうけんめい、考えてるところだよ!」というコメントを添えて展示する。「はじめはこんな形だったけど、こんなふうに変わっていったよ!」というプロセス展示のコーナーを設ける。「ここからどんな作品になるのかな?」と保護者が考えられる展示スペースをつくる…。そうすれば「ここが難しかったよ」「がんばったね!」といった親子の会話、家での会話も弾みます。
作品展は完成度を競う場じゃない
だから作品づくりの場面では「失敗しても大丈夫だよ」「自由にやっていいんだよ」と声をかけてあげましょう。そうすれば縮こまったり緊張したりせず、のびのびと自分の世界を広げていけるはずです。保護者に「作品づくりのプロセスやがんばりに注目してください」とアナウンスしておくのも忘れずに。
特別な材料を使わなくても、業務の負担になるような手間や時間をかけなくても、子どもたちと一緒にワクワクしながら展示会を開催することができるはずです。みなさんの園でも、ぜひ工夫してみてください。
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。