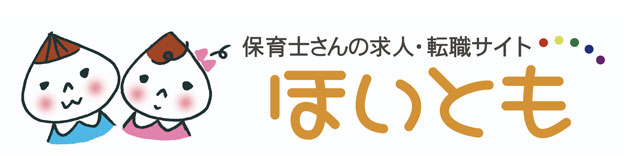2025.03.12
転職コラム
「ピアジェ理論」を取り入れた保育、その考えや取り組みって?

『ほいとも』ではこれまでにも、シュタイナー保育、モンテッソーリ園など様々な幼児期の教育法、導入保育園・幼稚園の様子などを紹介してきました。今回は「ピアジェ」のお話です。「ピアジェ理論」とはどんな教育方針なのか、保育現場にどう取り入れられているのか、理論に基づいて具体的にどんな保育を実践しているのか…。詳しく見ていきましょう。
「ピアジェ」理論って?
スイスの心理学者、ジャン・ピアジェは新生児〜青年期の発達段階を科学的にとらえ、「発生的認識論(genetic epistemology)」を提唱しました。これが一般に「ピアジェ理論」と呼ばれています。彼はまず、子どもがどうやって知識を獲得し、世界を理解していくかを4つの段階に分けて説明しています。
◆感覚運動期(生後0~2歳)
感覚と運動が発達の中心で、身体的な行動を通して世界を理解し始める時期
◆前操作期(2~7歳)
言語の発達や記号の理解が進み、数・形・色などの抽象的な概念が分かるようになる時期
◆具体的操作期(7~11歳)
数や量の概念が成立し、具体的な物事を自分で操作して経験を積み重ねる時期
◆形式的操作期(11歳~)
論理的推論が発達し、具体的な物事に頼らず数学などを形式的に解けるようになる時期
みなさんが接するのは0〜5歳児ですから、ここでは「感覚運動期」と「前操作期」を掘り下げます。それぞれの段階で子どもたちが何を認知し、何を認知していないのか。何ができて、何ができないのか。どんな遊びや活動が有効か。理解しておけばきっと、保育現場でも役立つはずです。
「感覚運動期」は、触って動いて成長
「運動」では、自分で動くことのすべてが発達につながります。給食やお弁当などの食事、着替え、片付けなども、子どもにとってはすべてが自分で動く体験になります。また異年齢保育の時間を作って年上の子どもたちと接する場を持てば、「自分もやってみたい」「あんなふうになりたい」という憧れが、運動能力をさらに発達させます。
「前操作期」は、まだまだ自己中心
ただこの時期は、まだ相手の立場で考えることができません。自分が欲しいものは欲しい。自分が楽しいことは相手も楽しい。自己中心性の考えから衝突やけんかが起きやすくなります。でも同時にトラブルを経験して、他者の目線や思いも理解していきます。保育士にはしっかり観察すること、適正に対処することが求められますね。
他者への理解では、人形遊び、ごっこ遊びも重要性を持ちます。人形の視点を通してまわりを意識したり、ほかの子を演じることで相手の気持ちを理解するようになります。そして模倣期にはお母さん役・先生役など大人のまねをすることで成長していきます。
「ピアジェ理論」を取り入れている保育園では…
具体的には「子どもが遊びを始めるきっかけをつくる」「遊びに集中できるスペースを整える」「自分から進んで遊べるおもちゃ、進んで何かを作ろうとする素材を準備する」といった取り組みをしているようです。そして発達に有効な遊びとして、ブロックや人形、絵カードのほかにペタペタシール遊び、算数セットなどを積極的に取り入れています。ごっこ遊びでは、お店屋さん、お医者さん、テレビのヒーロー・ヒロインなど幅広い役を設定し、そこからストーリーのある劇遊びへと発展させる園もあります。
ピアジェ理論を実践したい人は導入園に転職するのも一手ですし、『ほいとも』でも導入園を紹介できます。でも保育にはいろんな理論がありますので、まずはどんな保育が自分に合うかを考えるのもいいと思います。興味ある人はぜひ、こちらも読んでみてください。
◆ピラミーデ保育 https://www.hoitomo.jp/special/457/
◆シュタイナー保育 https://www.hoitomo.jp/special/603/
◆インクルーシブ保育 https://www.hoitomo.jp/special/636/
◆さくらさくらんぼ保育 https://www.hoitomo.jp/special/673/
◆モンテッソーリ教育 https://www.hoitomo.jp/special/770/
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。