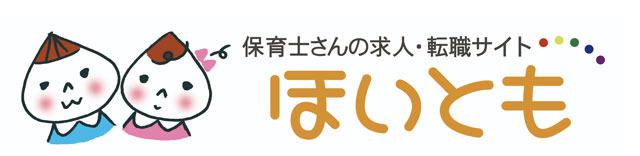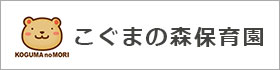2025.04.09
転職コラム
新年度、不安やストレスいっぱいの保育園児には、いつも以上のケアを!

新しい生活が始まる新年度。大人でも環境の変化に不安を感じたり、緊張したりしますね。幼い子どもたちにとっては、なおさらのこと。保育士には園児の変化に気づき、ストレスを軽減する対応が求められます。では具体的に園児のどんな様子や行動に注意し、どんなサポートをすればいいのか。詳しく見ていきましょう。
「五月病」は大人だけのものじゃない
新年度スタート後に体調を崩したり、気力が減退したりする「五月病」。環境や生活リズムの変化、新しい人間関係への対応、理想と現実のギャップなどが原因とされます。新大学生や新入社員によく見られますが、これは大人だけの問題ではありません。新しい生活が始まり、新しい先生や友だちと接することになるのは保育園の子どもたちも同じです。
もちろん子どもは自分が五月病だという自覚はありません。保育士が子どもたちの様子を注意深く見守り、サインに気づいて対応する必要があります。サインとは、例えばいつもに比べて「意欲がない」「すぐに泣く」「怒りっぽい」「元気がない」「食欲がない」「午睡をしない」など。さらに精神面のストレスが、頭痛・腹痛・発熱が続くなど健康面に影響を与えることもあります。
いつも以上に園児に寄り添いましょう
また「元気がない」場合は、ゆったり過ごさせてあげることが大切です。「早く!」と急かさず、子どものペースを尊重してあげましょう。逆に「午睡をしない」子には、外で太陽を浴びて遊ぶことが必要かもしれません。体を動かせば心地よい疲れが出て、気持ちもリフレッシュでき、リラックスして午睡ができるようになるはずです。
「食欲がない」子に無理に食べさせるのもNGです。栄養バランスの取れた食事を提供することも大事ですが、食事の楽しさを演出することで食欲が増進することもあります。「うわぁ、おいしそうだね」「先生もこれ、好きなんだ。一緒だね!」といった声かけをしてみましょう。いずれの場合もポイントは一人ひとりの子どもに、いつも以上に寄り添ってあげることです。
新入園児だけでなく、進級児にも注意
新入園児と比べたら変化は少ないかもしれませんが、進級児にも新年度ならではの不安や緊張があります。例えば担任が変わって指示が伝わりにくい。そんなときは前担任に相談です。3月まで普通にできていたことが急にできなくなる。そんな場合は「前はできてたのに」と思わず、あらためて「できたね!」と褒めてあげましょう。「この子はいつも元気だったから大丈夫」と高をくくらずに、進級児にもいつも以上の注意を払いましょう。
乳幼児については新入園・進級の差はありませんが、やはりいつも以上の配慮が必要です。例えば泣いてばかりの子は、泣くことで「自分はここにいます!」と訴えています。「先生はそばにいるよ」と声をかけ、背中にそっと触れるだけでも安心感を与えることができます。
自分の体調管理と保護者の協力も不可欠
また保護者の理解と協力も欠かせません。子どもの様子がおかしいと感じたら保護者にも詳しく伝える。逆に家で変化がないかを尋ね、情報を共有する。園だけで解決できない場合は「家でも少し甘えさせてあげてください」「お子さんの話をよく聞いてみてください」とお願いする。より多くの大人の目とケアで、子どもたちの不安を取り除いてあげましょう。
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。