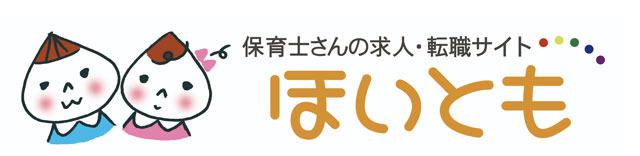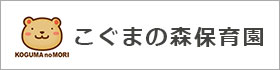2025.04.23
お役立ち情報
さぁ外遊びの季節!保育士として万全の環境整備・安全対策を!

様々なおにごっこ、砂場遊び、ドロ団子作り、ブランコやすべり台、フラフープやなわとび、そして自然観察…。子どもたちが大好きな外遊びの季節がやってきました。でも何より安全が第一。子どもたちが元気にのびのび遊べるように、環境整備や対策が欠かせません。当然みなさんの園でも行っていると思いますが、この機会に漏れがないかをチェックしてくださいね。
外遊びの重要性を再確認しておきましょう
おにごっこなど思い切り体を動かす遊びは運動能力を、すべり台などの遊具遊びはバランス感覚を向上させます。チーム遊びは社交性や協調性、問題解決能力を養い、砂場遊びやドロ団子作りは手先の器用さや創造力を養います。そして植物や昆虫とのふれあいは自然への敬意や興味を引き出し、感受性を育みます。
さらに外遊びは子どもたちの「いま」だけでなく「将来」にも好影響をもたらします。スポーツ庁の「体力・運動能力等調査」では、乳幼児期によく外遊びをしていた子は、その後も日常的に運動する割合が高いと報告されています。そして日常的に運動している人ほど「生活が充実している」と答える割合が高いそうです。
最近は外で遊ぶ子どもが減ったといわれます。ゲームなど室内遊びの充実、防犯上の問題、さらに危険だからと公園の遊具が次々に撤去されたり…。せっかく公園に集まっているのに隅のほうでカードゲームに興じている子どもたちを見かけることもありますね。そんな中、保育園の外遊びの大切さがあらためて注目されています。
まずは園庭や遊具の点検・メンテナンス
こうした事故・事案を防ぐには園庭や遊具の点検が最重要。園庭では地面が均一にならされているか、穴や凹みがないか、排水がスムーズにできているか。フェンスやゲートは、しっかり閉まるか、破損などで隙間ができていないかに加え、鋭利な突起が出ていないかも。最後に園庭全体を見て障害物で死角になっているところがないかも点検しましょう。
遊具は種類によって安全基準や法的規制があり、専門家による定期点検が必要だったりしますが、保育士によるチェックも欠かせません。すり減り、割れ、塗装の剥がれ、錆び、突起の有無など、見たりさわったりして分かることは常に確認したいですね。
点検については点検リストを作成し、月一度など定期的に行うこと、職員全体で情報を共有することが重要です。もちろん問題が見つかった際はすぐに報告し、修繕などの対策を。早期の発見、迅速な対応が事故防止の第一歩です。
事前にできる準備や対策を徹底しましょう
猛暑日が多発する最近は、これまで以上の暑さ対策も欠かせませんね。園庭を覆うシェードの使用を検討している園では早めの手配を、すでに使っている園では破れや傷みがないか早めの確認を。さらに「32度を超えたら外遊びを中止」「子どもたちには45分ごとに水分補給」というようにルールを作っておくのも大切な準備です。
万が一、ケガや熱中症が発生したら…。これも事前にルールや手順を決めておけば、あわてることがなくなります。薬や冷却剤などはどこに置いておくか。園で応急処置ができない場合はどうするか。保護者への連絡はどのタイミングで誰がするか。分かっているようなことでも、きちんと表などにまとめておくことをオススメします。
年齢や発達段階を考慮することも忘れずに
さじ加減が難しいとは思いますが、これは毎日子どもたちと接して、個性や特長をしっかり把握している保育士にしかできないことです。言い換えれば保育士の取り組み方次第で外遊びがもっと楽しくなるはずです。たいへんですが、子どもたちのために園全体で協力しながら頑張りましょう!
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。